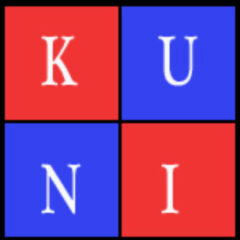高市早苗首相の台湾有事をめぐる国会答弁に中国当局が反発し、日本への渡航自粛や日本産水産物の実質的な輸入停止、さらには日本の芸能人らの中国公演を突然中止するなど、一連の対抗措置を講じました。その後もまぁ、いろいろと嫌がらせが続いていますね。
一方で、景気が冷え込む中国にとっては、日本企業の中国展開は経済面、雇用面からも非常に重要です。ポケットに手を突っ込んだまま偉そうにしてた中国外交局長も、その直後には撤退を恐れて日本企業詣でをしていたとか。
この情報の信憑性は分かりませんが、国内経済がボロボロでその批判の矛先が政府に向けられるのを恐れ、国民の敵意を日本に向けさせたい中国にとっては、今以上の景気悪化は一番痛いところ。最近台湾メディアが、キヤノンやソニーといった企業が中国工場を閉鎖しているなどとして、「日本企業が相次いで中国に別れを告げている」と報じたようです。
台湾のこの報道、中国との情報戦の色合いが非常に強いことを差し引いても、日本企業の中国からの撤退は十分起こりえる状況ですし、日本政府としても外交カードの一枚として上手く使っていきたいネタです。