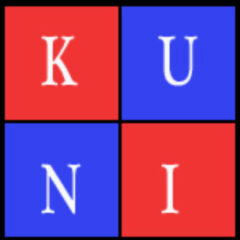最近インスタントラーメンにはまっていて、昔はよく食べていた「うまかっちゃん」を探しています。東京では大手のスーパーでも取り扱ってないみたいで途方に暮れております。
製造元のハウス食品のHPで確認してみると、販売地域という説明があり、「近畿、中四国、九州、沖縄県」と明確に宣言されていました。うまかっちゃんには何種類かのラインアップが用意されていて販売地域も微妙に違ってるんですが、いずれも東は近畿圏まで。中京、関東以北では売る気ないみたい。
なんでこんな方針なんでしょう。同商品は九州の民には「これぞ博多とんこつ」として大人気のラーメン。関東にも九州出身者たくさんいるだろうに。九州の福岡工場で製造されているから、輸送コストの問題?いやいや袋麺の輸送コストなんてたいしたことないだろうに。
ハウス食品という大手にもかかわらず(ラーメンはそれほど本気じゃない?)、西日本限定という同社の対応には異議を申し立てたいです。ネットで買えよってことかもしれませんが。