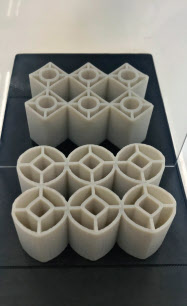6/4付け日本経済新聞に「独立アドバイザー 存在感 資産形成で個人に助言 金融機関に属さず中立性強み 業界団体、今夏に設立」という記事がありました。何だか記事の見出しが最近やたらと長いんですが、、、。
kuniが証券界に居たころから既に気配はありました。支店の営業員がパラパラと辞めていき、気が付くとどうやら繋がりのある営業員がセットで退職してIFAに、、、なんていうことが。まぁ、退職の理由はいろいろなんでしょうが、IFAになるというのはかなり有力な選択肢になりつつあることは確かなようです。
顧客本位の業務運営
証券会社、特に総合証券の営業員は3年に一回とかの転勤があり、顧客と長いお付き合いが難しいという問題がありました。顧客側からも担当者がころころ変わることに対する不満はよく聞きましたね。そういう面では、転勤のないIFAは生涯のパートナーになりうるというわけです。
また、もう一つ大きいのが、営業員が顧客に勧めたいと思わない商品でも、販売しなければならない場面があるということ。引受をやっている限り、引き受けた商品(株式や債券)を必ず誰かに買ってもらわなければなりません。たとえ、営業員が今この商品を買うべきではないと思っていたとしてもです。独立系ではこのようなお家の事情がありません。
一方で、引受部門があるからこそ、IPO(新規公開株)が手に入る、なんていうメリットもありますが、これもすべての顧客に渡せるわけではありません。トータルで見ると独立系の方が顧客に優しいでしょうね。記事が書いているように、まだまだこれからIFAになる証券マンは増加すると思います。
証券会社側にも組織上の問題が
このように証券会社から独立したIFAの方が、顧客にとっては頼りになりそうなんですが、証券会社側にも似たような事情があるような気がします。調査部門、引受部門、海外部門、法人部門といった部門をたくさん持つ総合証券会社では、部門間で様々な問題が発生します。
先ほどの、引受玉(引き受けた商品のことで「ギョク」と読みます)の問題もそうですね。引受部門が顧客に喜ばれるようなディールでは、それを販売した顧客には喜ばれない結果になることが少なくありません。一種の利益相反が起こるわけです。昨年のソフトバンクのIPOなんかがそうです。
また、引受部門や調査部門が非公開情報を入手した場合は、その情報が営業に使われないように、高度な情報管理が要求されます。この情報隔離という管理が破綻した事例が、今回の野村證券の東証市場区分情報の漏えいという事例であり、SMBC日興で起きたインサイダー取引等です。
システム投資も含め、相応にコストをかけて情報管理するわけですが、それでも上手く管理しきれなかった場合は、世の中の信用を失うという、さらに大きなコストを迫られることになるわけです。全国に支店を構えて営業員を配置していることも含めて、これらの膨大なコストを抱えたままでは採算が合わなくなってきているということですね。ちょっと長くなりましたので、続きは明日にでも。